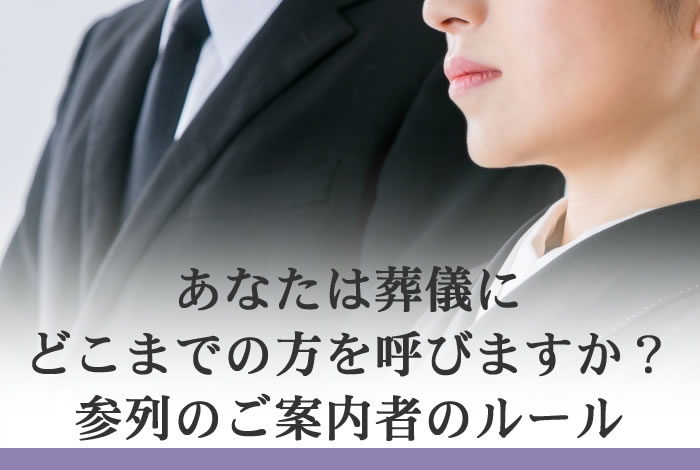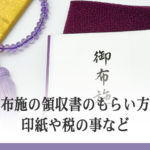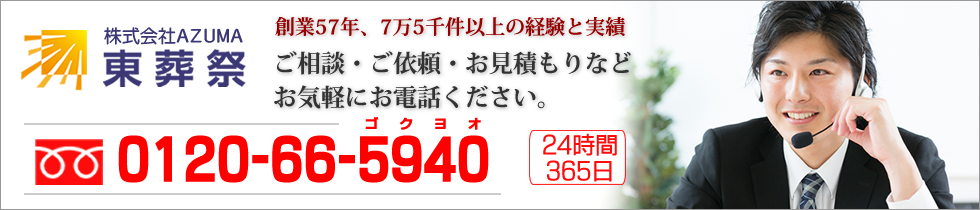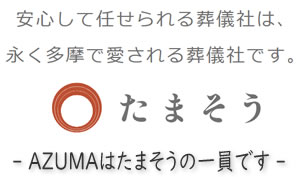お葬式にどこまでの人を呼ぶべきかは、喪主の頭を悩ませる問題です。
家族葬でしたいという家族の意向。
一方、あとあとの付き合いを考えて呼んでおいた方がいいかもしれない関係性。
どこまでの人を呼ぶべきかに、決まりやルールはないのですが、その考え方の基準をまとめました。参考にしていただければ幸いです。
家族葬の普及のおかげで、参列辞退に理解を示す人が増えた
平成に入り、葬儀の形は家族葬が主流になりました。血縁や地縁や会社関係など、これまで大切だとされていたあらゆる人間関係が希薄化していったこと、高齢化社会で故人と仲の良かった人の参列も同じように高齢で困難になったこと、さらにはバブルの崩壊で、小規模の葬儀が求められるようになったことがその理由に挙げられます。
それにともない、少し前までであれば、葬儀を家族だけで行うことは社会的なタブーでしたが、家族や親族以外の参列を断ることに、社会全体が一定の理解を示すようになりました。
しかし、お葬式はあくまでも人間関係の延長です。
社会の風潮とは関係なく「最後に顔を見たかった」「あんなに付き合いしてたのに声をかけてもらえずに寂しい」などの苦言を呈されてしまうこともあるようです。
たしかにお葬式の方針を決めるのは喪主の自由です。しかし、亡くなった本人にも「弔われる権利」がありますし、故人とつながりのあったすべての人に「弔う権利」があります。
故人のことを思うがために、こうした人たちは苦言を呈してくるのです。
だからこそ、お葬式にどこまでの人を呼ぶかは、慎重に考えましょう。

親族の場合
家族葬の「家族」がどこまでを含むかの定義は、これは実に難しい問題です。家の事情によってさまざまだからです。
われわれもさまざまな後葬儀のお手伝いをさせていただいていますが、核家族5名程度の家族葬もあれば、遠方からのご親戚を親族を招いて30〜40名規模の家族葬になることもあります。
家族葬にこれといった定義はありません。あくまでも。喪主や遺族の判断、そして親戚との関係性によるのです。
しかし傾向として、会社関係や友人知人は辞退しても、親戚に関しては比較的遠方でも参列してもらうケースが多いように思えます。
21世紀になったからと言っても、日本社会はいまでも血縁や親縁を大切に考えている証なのかもしれません。
隣近所や自治会の場合
故人様が亡くなったあとも、喪主やその家族がその上に住み続けるということもあるでしょう。その場合、近隣住民との付き合いはたいせつな事柄です。今後の付き合いを考えて、隣近所や自治会には声をかけていた方がいいというケースもあります。
いまでも、隣保や自治会の中で冠婚葬祭について取り決めているところもあるので、その場合は自治会長や、詳しい人に確認しておきましょう。
また、もしも故人様を自宅に安置する場合、斎場への参列はないものの、ご遺体が自宅を出発する時だけ見送ってもらうケースも多く見られます。
会社関係の場合
勤務先の会社へは、必ず忌引きの申請をしなければならないために、何も伝えずに密葬にする、というわけにはいきません。
社員の家族への参列は、会社の風土によっても異なるので一概には言えませんが、通夜や告別式に呼ぶことで職場に迷惑がかかることなどから、辞退するケースが多いようです。あるいは部署の上司など、代表者が参列するケースも見られます。
もしも弔問辞退、香典辞退を希望するのであれば、その旨ははっきりと会社側に伝えておきましょう。
友人・知人
もしも故人と仲良くしている人がいるならば、お葬式に呼ぶにせよ、呼ばないせよ、まずは不幸の事実を伝えましょう。
遺族が故人の友人や知人についてすべてを網羅しているわけではないので、代表の人を通じて訃報を伝えてもらうようにお願いするのがよいでしょう。
弔問を上手に辞退する方法
家族葬を希望するために参列を控えてもらう一番の方法は訃報を流さないことです。葬儀を終えたあとの事後報告にして、「故人の遺志により」家族葬をした旨を伝えると、多くの場合、理解を示してくれます。
また最近では、年賀欠礼、いわゆる喪中ハガキをもって事後報告とする人が増えています。
弔問辞退のデメリット
弔問を辞退して家族だけで葬儀を行うメリットもたくさんあるのですが、その分デメリットもあります。
事後報告で気をつけなければならないのは、その後の対応です。最も多いのは「せめてお線香だけでも」と自宅に弔問に来られた時の対応です。
葬儀式場であれば、お参りの時間と場所が整えられていますが、自宅への弔問はこちら側の日常的な時間を奪われてしまいます。無下な対応もできませんし、仏間に上がってもらう以上、お茶を出して、お話しの相手をしてと、予想以上の労力を強いられます。
それでも、葬儀の本質は、亡き人の顔を見て、生前の感謝を伝え、あの世での安寧を祈ること。亡き人と出会うことが大切である以上、参列を辞退するか、受け入れるべきか、慎重に考えていただきたいものです。