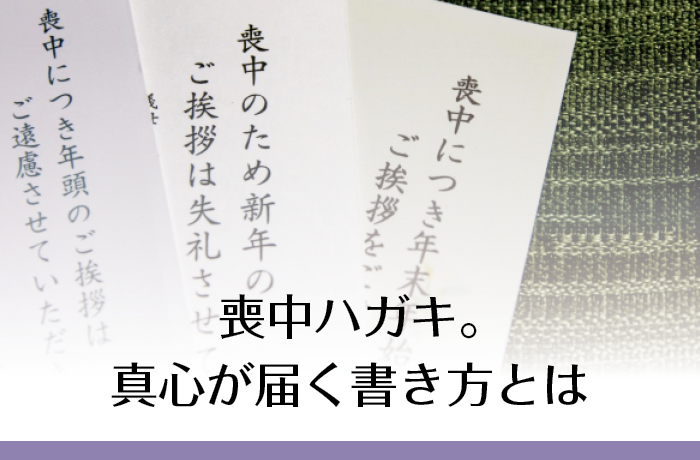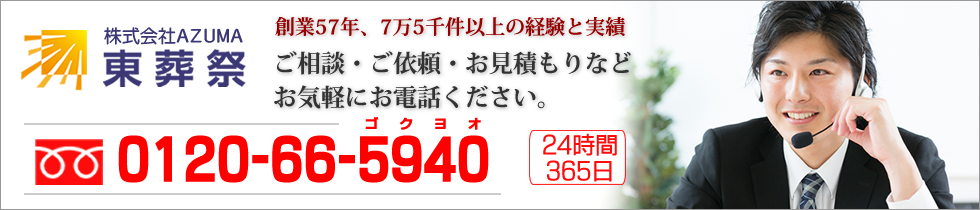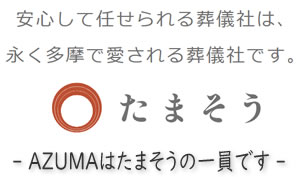時代とともに葬儀や供養の形も多岐にわたり、宗派にこだわらず多様な供養ができるようになりました。
従来であれば、墓石を建立して、その中に遺骨を納める方法が一般的でしたが、最近はさまざまな供養の方法が登場しています。
その中でも、遺骨を身近な場所に置いておく「手元供養」が選ばれています。
ここでは、遺骨や遺灰を納めて携帯できる「遺骨ペンダント」を中心に、手元供養がどのようなものなのかをご紹介していきます。
故人を身近に感じられる「遺骨ペンダント」
「遺骨ペンダント」とは、故人の遺骨や遺灰、遺髪などを納められるもので、メモリアルペンダント、アッシュインペンダント、納骨ペンダントなどとも呼ばれています。
最近では「故人を身近に感じていたい」「いつも近くで見守っていてほしい」という遺族の方に、遺骨などの一部をお墓に埋葬せず、何らかの形で身近に残して供養する「手元供養」という方法も増えてきました。
中でも「遺骨ペンダント」は身につけていられるという点で人気があるようです。
このような供養ができるようになったのも、お墓が遠方でお墓参りが困難という場合や、家に仏壇を置かない家庭が増えたことも理由の一つです。
ペンダントのほか、指輪やブレスレットなどもあり、より遺族の気持ちに合わせた供養の形となっているようです。
遺骨ペンダントの使い方
ほとんどの遺骨ペンダントはチェーンの先端のエンドパーツに遺骨が納められるようになっています。
ご存じの通り、ペンダントのエンドパーツは、手のひらに乗るほどの小さなものです。ですから、その中に納める遺骨もほんのごく一部です。
遺骨の破片をさらに小さく砕いて、粉状にしたものを中に納めます。
火葬場から引き取った遺骨全てをペンダントの中に納めるというのは難しく、分骨した一部をペンダントに納めるものとして考えておきましょう。
遺骨ペンダントの注意点
遺骨ペンダントは、肌身離さずに故人様を感じられるという点で人気があります。
しかし、ペンダントそのものを携帯することになるので、万が一の紛失には充分に気をつけましょう。
また、手元供養とはいうものの、最終的にはペンダントの中の遺骨も何らかの形で処理しなければなりません。
たとえ微量の遺骨とはいえ、れっきとした遺骨です。
どこかのタイミングでしかるべき場所に埋葬する、あるいは自身の骨壷の中に副葬品として納めるなど、他の人の迷惑にならないように、その取扱いについて事前に考えておきましょう。
その他のさまざまな手元供養アイテム
手元供養とは、遺骨ペンダントだけではありません。
その他にもさまざまな手元供養のアイテムが販売されています。
- ジュエリー(リング、ブローチなど)
故人様の遺骨を肌身離さず身につけておくものとして、リングやブローチやブレスレットなど、ペンダント以外のジュエリーもあります。シルバー製品はお手頃の価格で手に入りますが、ダイヤモンドや18金やプラチナ製のものもあり、幅広い予算や種類から選べます。
- ステージ
ステージとは、遺骨や写真を置くための小さな祭壇です。仏壇のような決まった形式はなく、現代の住空間にあったコンパクトなデザインが特徴です。特定の宗教の本尊を祀ることなく、遺影や骨壷、あるいは故人を表すモニュメントのような位牌などを安置して、手を合わせます。
- ミニ骨壺
火葬場で納められる骨壺は陶製の質素なものですが、最近は、手元供養として自宅でお祀りできるよう、さまざまなコンパクトでオシャレな骨壷が販売されています。陶製、金属製、ガラス製、漆器などがあります。
- フォトスタンド
フォトスタンドは、遺影を飾っておくためのものです。通常の写真立てとは異なり、ウォールナットやベネチアガラスでできたフォトスタンドなどがあります。さらには、ステージと一体型になったものや、プリザーブドフラワーの装飾を施したものなど、さまざまなバリエーションで故人様の面影を偲べます。
- モダン位牌
位牌とは、従来は故人様の戒名や命日を刻んでおく木の板のことでした。しかし、最近の位牌には、戒名を刻むとは限りません。故人様の生前の名前、あるいは故人様を象徴する言葉などを刻んで自宅の中で祀ります。いわば、魂の込められる位牌ではなく、故人様を偲ぶモニュメントのような役割を果たしているといえるかもしれません。
供養する気持ちを大切に
これだけ手元供養が普及して、多くの人に認知されているとはいえ、その反面、分骨をしたり遺骨を身につけたりすることに抵抗がある方もいます。
分骨や遺骨を仏壇やお墓ではない場所で保管する、あるいはアクセサリーに納めることについては、法律上の問題はありませんが、供養する方の気持ちが大切です。
供養の形にはいろいろな選択肢があります。
どうしても遺骨を身近に置いて手元供養をしたいのであれば、のちに遺族間でトラブルにならないよう、十分に話し合いをしておく、あるいはこちらの想いを伝える取り組みが求められます。