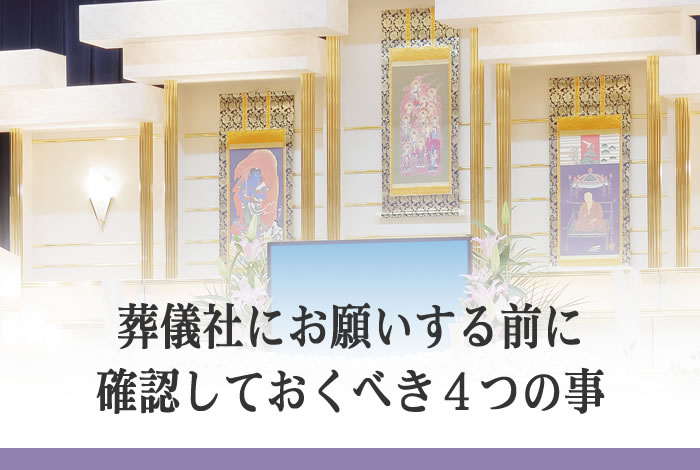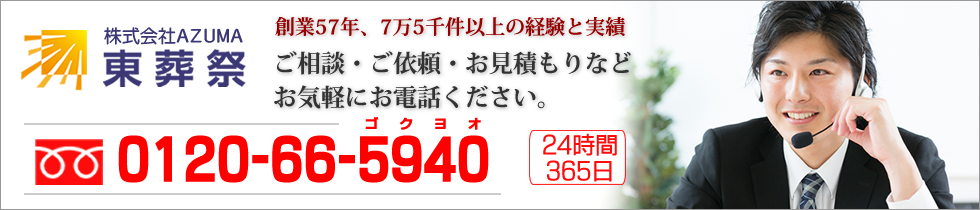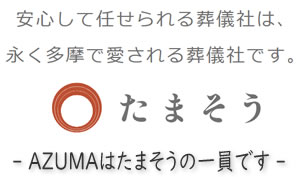葬儀は、いつやって来るか分からず、すぐに取りかからなくてはならず、高額な費用がかかってしまいます。
突然のことに戸惑い、悲しみに暮れる間もなく、喪主や家族はさまざまなことを手配しなければなりません。そのためトラブルに見舞われることもしばしば。
この記事では、大切な人の最初で最後の葬儀を後悔のないものにするために、葬儀社にお願いする前に確認しておくべきことをまとめました。ここに挙げた4つを事前に考えておくだけで、いざという時の負担は大きく軽減されるでしょう。
菩提寺があるかないか
菩提寺とは、先祖代々を供養してくれているお寺のことです。もしも菩提寺があるならば、葬儀には菩提寺に来てもらいます。菩提寺があるにもかかわらず、他の寺院で葬儀を行ってしまうとのちのちのトラブルにもなりかねません。
「遠いから」「最近付き合いがないから」というような家族側の一方的な想いで、近くの寺院を依頼しがちですが、このあたりは慎重に判断しなければなりません。遠方でも足を運んでくれる寺院はたくさんありますし、疎遠とはいえ境内にお墓があればそこに納骨するわけですから、菩提寺を無視するわけにはいきません。
実際に、葬儀を別のお寺でおこなったことで、お墓に納骨できなというトラブルも起きています。あとでいやな思いをしなくてもいいように、菩提寺の有無はきちんと確認しておきましょう。
宗派の確認
仮に菩提寺がないのであれば、葬儀を行う時に葬儀社に寺院を紹介してもらいますが、あわせて宗派を決めなければなりません。喪主が自由に決められるのですが、たくさん宗派がある中でどこを選ぶべきか判断に迷うものです。その時によく選ばれるのが、本家や親戚の宗派にあわせるという方法です。事前に宗派を把握しておけば、いざという時にもスムーズに進められます。
参列者をどこまで呼ぶか
最近は家族葬が多いため、家族と親族だけの葬儀が当たり前のようになりました。
家族葬にはいい面と悪い面があり、葬儀の手間や費用が省ける分、葬儀後の対応の負担が大きくなります。自宅に弔問に来られた場合はその都度対応をしなければなりません。
また、どこまでの人を呼んでどこまでの人を呼ばないかの線引きによって相手を不快な思いにさせることもあるかもしれません。
これらの方針をあらかじめ決めておくことで、葬儀の打合せはよりスムーズに進むでしょう。
ご遺体の安置場所
故人様の安置場所をあらかじめ決めておきましょう。というのも故人様が息をひきとると、遺族はすみやかに葬儀社に連絡して遺体をどこかへ搬送しなければならないからです。主に自宅か、葬儀社などが保有する安置施設が選ばれます。自宅に連れて帰る場合、ご遺体を寝かせて祭壇を設置するスペースを確保しておきましょう。また、もしも家族葬を希望していて近隣の人たちに知られたくないのであれば、自宅ではなく安置施設を利用するのが賢明です。
遺影写真の準備
葬儀の打ち合わせの障害になりがちなのが遺影写真です。たくさんのことを決めなければならない中で、遺影写真にどれを使おうか、家中をひっくり返して故人の生前の写真を探すという光景も少なくありません。特に写真に映ることが苦手としていた人の場合、写真そのものが見当たらないということもしばしばです。ですから、事前に遺影に用いる写真を用意しておけば、打ち合わせもスムーズに進みます。最近ではスマートフォンでの撮影がとても多いため、わざわざプリントしなくても、データを葬儀社に預けるだけで構いません。ただし画素数やピントが合っているかなどの点に気をつけましょう。
費用・見積もり
さまざまな葬儀社が、葬儀費用をセットプランとしてパッケージしています。プランの中に何が含まれているか、なにがあとから追加費用が発生するかを可能な限り把握しておきましょう。一番良いのは複数の葬儀社から見積もりをとることです。葬儀費用の概略が理解でき、葬儀社別の見積金額も提示されるでしょう。
東葬祭では、お客様目線に立って常に明朗会計に努めています。葬儀はただ安ければよいわけではありません。何にどれくらいの費用がかかるのかをきちんと分かりやすくお伝えした上で、お客様の想いやご事情に寄り添ったご提案をさせていただきます。
葬儀社の人柄や仕事ぶり
葬儀は「モノ」の購入ではなく、「人的サービス」の享受です。満足度を一番大きく左右するのは、式場でも祭壇でも費用でもなく、葬儀社スタッフの人柄や仕事ぶりだとも言われています。もしも複数の葬儀社を見て回る余裕があれば、見積もりや費用だけでなく、対応する社員の人柄にも着目してみましょう。
東葬祭の社員は、みなが真面目で葬儀に対して一生懸命です。勤務体系や労働環境がどうしもて悪くなりがちな職種ですが、お客様からの「ありがとうございます」という言葉を励みに、日夜お客様にとっての最良のお葬式について考えています。どんな些細なご要望やわがままにも誠心誠意お応えるのは、社員ひとりひとりが葬祭業の崇高さを身に沁みて感じているからにほかなりません。